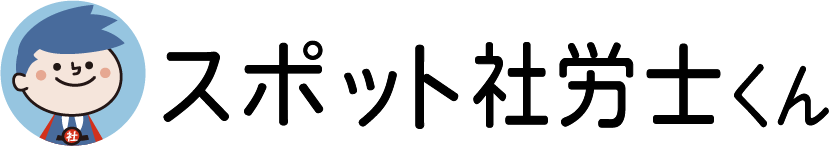NEWS
2020.09.29
36協定の労働者代表の押印が不要に!労働者代表の選出の流れ
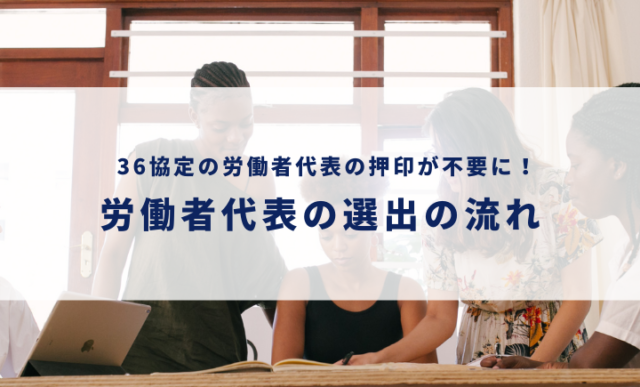
日本経済新聞に、「企業の労使協定書類で押印廃止 厚労省、21年度から」(2020年9月6日付)という記事が掲載され、話題となっています。
36協定などの労使協定は労働基準監督署に届け出ますが、その届出には労働者代表の押印が必要です。押印のないものは不備となってしまうため、書類作成時の重要なポイントのひとつでもあります。それがなぜ廃止になるのでしょうか?
この記事では労使協定書類の押印が廃止される理由と廃止による影響、労働者代表の有効性の確保について解説します。
労使協定押印廃止の理由
厚生労働省は、企業の業務効率化を後押しするため、労使協定の押印廃止を進めています。労使協定の代表的なものとして、「時間外労働・休日労働に関する協定書」があります。一般的に「36協定」と呼ばれる協定の届出書類です。
36協定は、従業員に残業をさせるためには必ず結ばなければならない協定です。
厚生労働省は、現在、届出していない企業や進め方がわからない企業に対して、労働局や労働基準監督署が講習会を催して協定締結および届出の強化を進めています。

そうした取り組みの効果もあり、36協定の届出件数は2015年(平成27年)には145万件であったものが、2019年(令和1年)には178万件まで増加しています。
新型コロナウイルスの影響や働き方の多様化に伴い、会社に出勤しない働き方も増えているなか、労使協定に押印するためだけに出社する社員もいるようです。
なお、36協定は電子申請システムによる届出も可能になっていますが、始まったばかりの制度であり、十分に普及しているとはいいがたい状況です。
こういった背景を考えると、企業の業務負担と作業効率のアップの観点から労使協定の押印廃止の流れもうなずけます。
押印廃止に伴い電子申請システムの電子署名も不要となりますので、電子申請のほうも今後は普及が進むと予想されます。

労働者代表の選出の有効性
労使協定の押印が廃止されても、労働者代表を選出しなくてよくなるわけではありません。労働者代表は会社側が指名することはできず、定められたルールに沿って従業員のなかから選定されます。
2018年(平成30年)の独立行政法人労働政策研究・研修機構の「過半数労働組合および過半数代表者に関する調査」では、過半数代表者の選出方法は「使用者の指名」と「特定の者が自動的になる」を合わせると27.6%となっており、ルール通り民主的な方法で選出されているとはいいがたい状態です。

今後は、押印の代わりに「労働者代表の選出の有効性の確保」が課題となりますので、正しい方法で労働者代表を選出するように注意しなければなりません。
押印廃止を受けて、労働者代表の選出方法はいっそう重要度を増すことが見込まれます。
労働者代表とは?役割は?
労働者代表は、労働者の代表として、使用者である会社との間で労使協定を締結する役割を果たします。
労働者の過半数以上で組織された労働組合があれば、労働組合の代表が労働者代表となることができます。
労働組合がない場合には、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にない者のなかから選任された者が労働者代表となります。

労働者代表の選出方法と流れ
労働者代表は、使用者である会社の意向に基づいて選出された者であってはなりません。パートやアルバイトを含む従業員(派遣社員を除く)に対して、「36協定の締結をする者」を選出することを説明して、投票、挙手等の方法で選出しれなければなりません。
会社による指名や、親睦会の代表を自動的に選出するなどの方法は不適切な選出となり、その者が結んだ労使協定は、労働基準監督署に届出がなされていても無効となりますので注意しましょう。 ただし、親睦会の代表をしている者を正しい選出方法で選任した場合は問題ありません。
【労働者代表の選出の流れ】
1.労使協定の締結当事者となる労働者代表を決めることを告知し、立候補を募る。
2.立候補者の経歴書を作成する。
立候補者がいなければ、会社側が推薦することが可能です。その場合は会社側の推薦として経歴書を作成します。
3.従業員全員に何の(例えば「36協定」や「○○規程変更」など)労使協定を結ぶための労働者代表を選出しているか明確に説明し、立候補者や推薦者について告示する。
4.民主的な方法により過半数代表者を選出する。
具体的な選出方法としては次のような方法が考えられます。
・投票による選挙や信任
・従業員の集まる場での挙手による選挙や信任
・書面の回覧による信任
・メールによる信任 など
クラウドシステムによるサービスもあります。
従業員のメールアドレス一覧があれば、質問項目が自動でセットされ、代表者選出がスムーズに行えるサービスもあります!
✅楽楽代表
https://www.spot-s.jp/daihyou/
5.過半数代表者が決まったら文書で周知する。
このようにして労働者代表を選任していれば「選出の有効性は確保できた」ことになり、労使協定の締結当事者や従業員代表として意見を述べる者として問題ありません。
労働者代表の記載のある書類を確認しよう!
36協定などの労使協定以外にも、労働者代表の記載のある届出書類はたくさんあります。それらの書類の内容ごとに労働者代表を選出しなければなりません。


たとえば、給与規程の変更届出の意見を聞くために労働者代表を選出した1週間後に、36協定を締結することになったような場合、改めて労働者代表を選出しなければなりません。
これは労働者代表を選出する時に従業員に対して「何のための労働者代表を選出しているかの説明」の部分に係るものです。
もし、改めて労働者代表を選出せず、規程変更のために選出した労働者代表と36協定を結んだ場合は、その協定は「労働者代表の選出の有効性が確保できていない」ため無効となります。
労働者代表が正しく選出されていないと労使協定や規程が無効に
労使協定の労働者代表の選出を例にご説明してきましたが、労働者代表の選出が正しく行われていないことで起こる問題点を、具体的な事例を元に確認してみましょう。
事例1. サンフリード事件
外勤手当などを固定残業代に置き換える就業規則変更の効力を争った裁判です。就業規則を変更し労働基準監督署に届け出ていましたが、その際の労働者代表を投票・挙手等により選出していませんでした。
そのため、労働者代表者の選出方法に不備があるとして、労働者代表の意見書から就業規則の条件変更に同意した事実を推認できないとしました。
引用:サンフリード事件
事例2.トーコロ事件
36協定を前提とした残業命令を拒否し、解雇された従業員が、解雇取り消しを争った裁判です。36協定を、役員と従業員からなる親睦会の代表者と締結しており、労働者代表の選出に民主的な手続きが行われていないとして、36協定が無効とされました。
36協定を前提とする残業命令は無効であることから、従業員はこれに従う義務はなく、残業命令を拒否したことを理由とする解雇は無効となりました。
引用:トーコロ事件
事例3.電通事件
従業員に違法に残業させていたとして調査を受けていた電通が、その調査過程で「36協定が無効」と指摘されました。36協定を締結した労働者代表の労働組合が過半数以上で組織されていなかったためです。
引用:電通の労使協定「無効」 労働者の過半数に達せず 東京地検が指摘
事例4.早稲田非常勤講師雇い止め紛争
早稲田大学では、非常勤講師に不利益となる就業規則の導入にあたり、非常勤講師以外の講師から候補者を7人選び、学内に掲示。正当な代表者選出の手続きを踏んでいる、と主張しました。しかし、実際には当該期間は試験真っ只中という多忙期で非常勤講師は学内に入れない時期であり、ほとんどの非常勤講師はこのことを知りませんでした。大学側の恣意的な「過半数代表者の選任」は、強引な手法であるとニュースになりました。
刑事告発され、東京地検により不起訴とされていましたが、東京第4検察審査会は「不起訴不当」と議決されました。
引用:早稲田大学で起こった「非常勤講師雇い止め紛争」その内幕(田中 圭太郎
事例5.乙山色彩工房事件
日本画・彫刻などの制作と修繕、お寺などの建造物の彩色などをする京都の工房は、社員らと専門業務型裁量労働制の労働契約を締結。しかし、実際には社員に裁量はなかったとして、未払いの時間外労働手当の支払いを会社に催告し、訴訟を提起しました。
それに対し、会社は、上記の裁量労働制の適応対象であるともに、対象の従業員のうちひとりが、労基法41条2号の管理監督者であると主張しましたが、労働者代表の選出方法が悪い(選出する会合や選挙を行なっていない)ことを理由に、裁量労働制の労使協定は無効と判断されました。
引用:乙山色彩工房事件(京都地判平29・4・27) 「専門業務型」のデザイナー、割増賃金を求める 裁量労働制 代表者選出といえず
事例6.セーフティーガード
熊本市にある警備会社セーフティガードは、違法な時間外労働をさせたとして熊本地検に書類送検されました。36協定は届け出ていたものの、過半数代表者が会社の指名した者になっており、有効ではないと判断されました。
引用:会社の労災申請から送検に 警備業者が違法残業をさせる 熊本労基署
事例7.丸光運輸
高知県で一般貨物自動車運送業を営む丸光運輸は、有効な36協定を締結せずに、時間外労働をさせたとして、書類送検されました。発覚のきっかけとなったのは、同社の従業員が運転中に、歩行者を死亡させる事故を起こしたことでした。この本人を過半数労働者として36協定を締結していたが、労働者代表とされた本人は書類に見覚えがないと供述したため、問題が明るみになりました。
引用:無効な36協定と判断 使用者が”代表者指名” 須崎労基署が送検
事例8.奥岡技研
輸送用機械機器製造業の奥岡技研は、労働者らと一切協議せず、無効な36協定を提出し、違法残業を行わせていたとして、書類送検されました。同社では、協議書を作った事務員にそのまま労働者代表の押印をさせ、届けていました。
引用:事務員を過半数代表に指名 違法残業として告訴――津労基署書類送検
まとめ
このように労働者代表の選出の有効性は非常に重要なポイントとなります。会社側が指名したり、民主的な選出方法を経ずに親睦会の代表者が自動的に就任する、といったことのないように適切な選出手続きを行いましょう。
参考:奈良労働局 36協定の締結当事者になる過半数代表者の適切な選考を!
クラスワークへのお問い合わせはこちらまで
オンラインセミナー(無料)のご案内

ネットで調べてもよくわからない人事労務の情報を手軽にオンラインで学べる! 様々なコンテンツをご用意しております。
スポット社労士くんから加入で
今なら1年間無料‼

毎月の給与計算をもっと楽に簡単にしたい!という皆様朗報です!
今ならクラウド給与ソフトが1年間無料!
参考記事