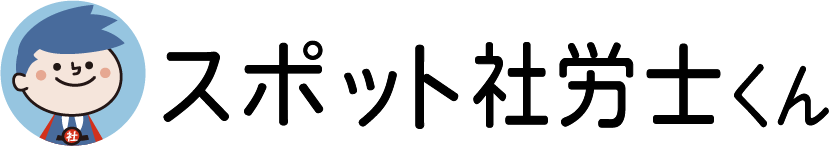有給休暇
2021.04.12
年次有給休暇の付与パターンについて
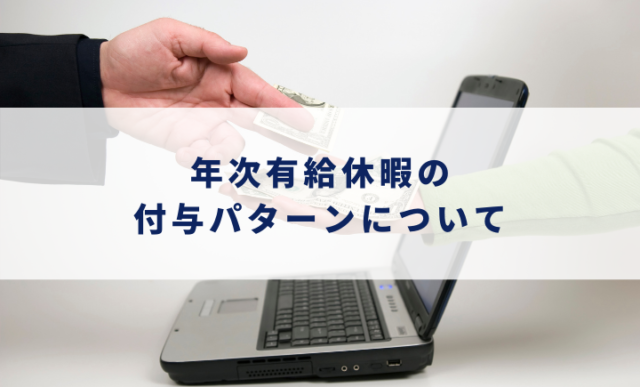
入社半年以内の社員も有給休暇を取得できるようにしたいのですが・・・有給休暇は入社後半年で付与するものですよね?何か方法はないのでしょうか?
年次有給休暇は、労働基準法で付与するタイミングと日数が定められています。しかし、それよりも社員に有利な条件で付与することは可能です。
基準日や付与日数・方法など、法定の付与のタイミング以外にもいくつか定め方がありますので、ご説明します。
有給休暇の付与に関する法律上のルール
有給休暇の付与については労働基準法第39条で、付与日数や付与の条件が定められています。
○有給休暇付与の要件
有給休暇は無条件で付与されるわけではありません。一定の要件をみたした場合に付与されるものです。
付与される要件は次の2つです。
1.6カ月間継続勤務していること
勤務の実態に即して実質的な在籍期間を判断します。社員身分が変更した場合は継続勤務と認識します。
例)定年後の再雇用、パートからの正社員登用など
2.全労働日の8割以上出勤していること
労働災害や育児休業・介護休業で休んでいる期間は出勤したものとみなして出勤率を計算します。また、会社都合の休業期間(一時帰休など)は、原則として、出勤率算定の分母となる全労働日から除外します。
○有給休暇の付与日数
有給休暇は入社後6カ月後に10日付与する定めです。通常は有休を付与する基準となる日を有休起算日といいます。就業規則で特別な定めをしていない限り、入社日が有休起算日となり、その後は1年ごとに勤続年数に応じた日数を付与するルールです。

○比例付与とは
比例付与はその労働日数に応じた日数を付与する方法です。対象者は次のように定められています。
・週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下の者
・週所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下の者
「パートタイマーやアルバイトだから比例付与の対象となる」というわけではなく、あくまでも労働日数が基準となりますので注意しましょう。
また、有給休暇の付与日数は、労働基準法のルール以上の待遇であれば法的に違反になりませんが、労働基準法のルールに満たない就業規則の定めは無効となります。
有給休暇の付与のパターンと就業規則の定め方
有給休暇の付与パターンについてご紹介します。原則として、法律で決められているより上回る日数を付与する場合が多いですが、その分、管理する負担が軽減されることになります。
(1) 一斉付与にする
一斉付与は有休起算日に関係なく、有給休暇を一斉に付与する方法です。付与日を年度始めなど特定の日に統一して管理の負担を軽減します。
中途採用の多い企業では、入社日を起算日にすると6カ月経過後に順次、有給休暇の付与をすることになります。そうしますと毎月のように有給休暇を付与する社員が発生します。
入社年度は6カ月経過後に有給休暇を付与し、翌年からは付与日を統一することで有給休暇の管理の煩雑さが軽減できます。
注意点は、統一した場合に法定の付与日数を下回らないことです。
また、有給休暇の付与日を統一すれば消滅日も統一できますので、管理する手間が大幅に減るでしょう。
就業規則には、一斉付与日を明確にして定めるようにしましょう。
例:毎年4月1日を基準として有給休暇を一斉付与する。
(2)有給休暇の起算日を毎月1日に統一する
有給付与の起算日を入社日ではなく入社月の1日に統一することで、有給休暇付与日が月内にバラバラと発生することを回避できます。
有給休暇の付与は6カ月継続勤務経過後となりますので、入社日を起算日とすると、6カ月後の付与日が同月内に複数発生することになります。
同月内に有給休暇の付与日が複数あれば、付与日の2年後に消滅する日も同月内に個人ごとに到来することになり非常に煩雑です。入社した月の1日に統一することで、管理負担を大幅に軽減できます。
注意点は毎月1日に統一することです。仮に給与の賃金の計算期間が21日から翌月20日の会社で21日に設定すると、20日以前に入社した社員の付与日が法定の継続雇用期間6カ月を超えてしまいます。たとえ数日でも法を守っていないことになります。
そういった意味で毎月1日にしておけば、1日に入社した社員には法定の基準通り6カ月後に有給休暇が付与され、20日に入社した社員には法定を超えた条件で有給休暇を付与することになり問題はありません。付与日を統一する時は注意しましょう。
就業規則には、有給休暇の起算日を明確にして定めるようにしましょう。
例:有給休暇の起算日は入社月の1日とする。
(3) 中途入社日から付与するパターン
有給休暇の一斉付与をしている場合で付与日よりも後に入社すると、次の一斉付与日までが6カ月以上となることがあります。その場合は、一斉付与日より前に有給休暇を付与しなければなりません。
例えば、4月1日を一斉付与日としている会社で、5月1日に入社した社員には11月1日に有給休暇を付与しなければならないのです。この場合は一斉付与のメリットである管理負担の軽減が享受できません。
このようなパターンを想定して最初から就業規則に有給休暇の付与日を定めることも可能です。
例:4月1日から9月30日までに入社した社員には入社日に10日の有給休暇を付与する。
10月1日以降に入社する社員に配慮したかたちで、
10月1日から11月30日までに入社した社員には8日、12月1日から翌年1月31日までに入社した社員には6日
のように入社日にあわせて細かく設定することも、法定の付与日数を下回らなければ問題ありません。そして翌期4月1日には一斉付与で12日を付与すればよいのです。
ここでの注意点は、期末日までの継続勤務期間を計算して法定を下回らないように付与日数を設定することです。
社員身分変更による有給休暇の付与はどうなる?
継続雇用などで社員身分を変更した社員の有給休暇の付与はどうなるのでしょう。社員身分が変更した場合でも、雇用期間と有休起算日は引き継ぎます。
38年勤務して定年を迎えた社員が短時間勤務や週の勤務日数が減った場合でも、継続勤務期間は38年と考えて有給休暇の付与日数を計算します。
ただし、勤務日数が減った場合は比例付与しても問題ありません。付与日の雇用形態で判断します。
例えば勤続38年で3月31日に定年退職し、4月1日から週3勤務の継続雇用となった社員には、週の労働日数3日で継続勤務年数6年6カ月以上の要件である11日の有給休暇を付与すればよいのです。
入社半年以内の社員も有給休暇を取得できるようにすることを就業規則で定めればよいのですね。しかし、有給休暇の付与は複雑ですね。
有給休暇の付与については、労働基準法で定められている以上の待遇をすることは問題ありませんので、その点に注意すれば就業規則の定め次第ですね。
就業規則を変更した場合は従業員の意見書をつけて、労働基準監督署に届出するようにしましょう。
また、就業規則で定める際の有休起算日や付与方法によって、管理の負担は大きくかわってきますので、その点も考慮するとよいですよ。
オンラインセミナー(無料)のご案内

ネットで調べてもよくわからない人事労務の情報を手軽にオンラインで学べる! 様々なコンテンツをご用意しております。
スポット社労士くんから加入で
今なら1年間無料‼

毎月の給与計算をもっと楽に簡単にしたい!という皆様朗報です!
今ならクラウド給与ソフトが1年間無料!
おすすめ記事