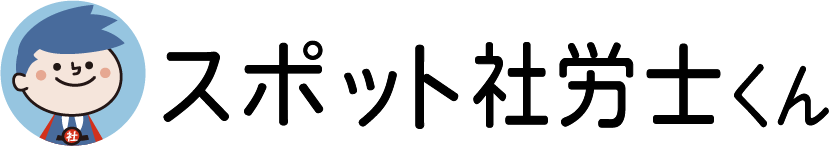労働問題
2024.04.04
労働保険とは?加入方法・計算方法や雇用保険との違いについてわかりやすく解説!
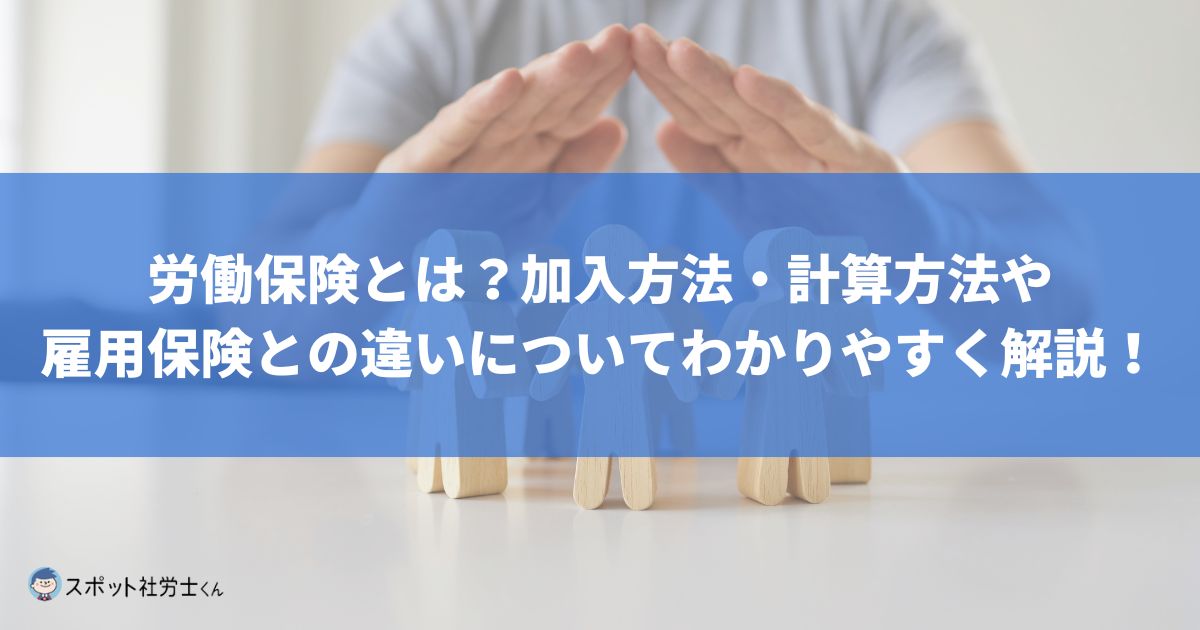
労働保険とは、労災と呼ばれる「労働者災害補償保険」と「雇用保険」を総称したもので労働者の安全や雇用を守る国の制度です。
今回は、労働者の安全に関わる労働保険について解説していきます。
労働保険の加入対象
労働保険は、原則として1人以上の労働者を使用する事業所はすべて加入しなければなりません。
本社のほかに支社や営業所等がある場合は、原則として個別に適用を受けます。
(ただし、所定の手続きを経て、一括申請ができる場合もあります)
一般的に労災保険・雇用保険の手続きは同時に進めますが、一部の業種では別個で申請が必要です。自社がどちらに該当するのか、確認しましょう。
グループA 一定の予定期間に終了する事業(有紀事業)【建設業等】
→労災保険・雇用保険を別々に申請(「二元適用事業」と呼ぶ)
グループB 期限が決まっていない事業
→労災保険・雇用保険を同時に申請(「一元適用事業」と呼ぶ)
労働保険の加入方法
労働保険の加入方法は、先述のグループによって異なります。
グループA 二元適用事業所
・労災保険
「労働保険保険関係成立届」を管轄の労働基準監督署に提出。当年度の概算保険料を申告・納付する
・雇用保険
「労働保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークに提出。当年度の概算保険料を都道府県労働局に申告・納付する
グループB 一元適用事業所
「労働保険保険関係成立届」を管轄の労働基準監督署に提出。当年度の概算保険料を申告・納付する
→控えをハローワークに持参。「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出。
労働保険料の保険料率
労働保険料は全労働者の賃金総額の見込み額×労働保険料率で支払います。保険料率は業種によって異なります。
労働保険料には以下の3種類があります。
- 一般保険料
- 特別加入保険料
- 印紙保険料
労働保険は原則、従業員が加入するものですが、飲食業や建設業等、危険を伴う作業を行う業種の場合は、特別に事業主も加入することができます。
これらについて詳しく解説していきます。
一般保険料【共通】:従業員の給与をもとに計算し、全額事業主が負担
【一般保険料率=労災保険料率+雇用保険率】
労災保険料率:業種ごとに、危険性を考慮して決定。全額事業主が負担する。
雇用保険料率:業種ごとに、3段階に区分。事業主と被保険者が折半する。
特別加入保険料【労災保険のみ】
第1種:中小企業の事業主、家族として従業する者が加入したときに払う
第2種:一人親方(事業主のみの会社)、個人自営業、家族として従事する者が加入したときに払う
第3種:国内の事業から海外派遣されている人が加入したときに払う
印紙保険料【雇用保険のみ】:事業主と日雇い労働者が折半して払う
厚生労働相の印が押された「印紙」を使用します。
収入によって印紙保険料は3段階に分かれます。
第1級 76円:賃金の日額が11,300円以上
第2級 146円:賃金の日額が8,200円以上11,300円未満
第3級 96円:賃金の日額が8,200円未満
実は、業務上・通勤途中の災害防止努力の結果に応じて、保険料の額を増減させる「メリット制」を適用することができるため、労災保険料は事業主の努力で抑えることができます。
労働保険料の申告・納付方法
労働保険料は毎年6月1日~7月10日までの期間に「年度更新」という手続きを行い、労働基準監督署や都道府県労働局に申告・納付します。
まず、事業主は新年度に1年分の概算保険料を計算して申告・納付します。そして、翌年度に確定保険料として清算します。つまり、事業主は前年度の確定保険料と、当年度の概算保険料を同時に申告・納付することになります。
ここで「概算保険料が40万円以上」等、所定の条件を満たす場合には「延納」という形で3回に分けて支払うことができます。以下は支払日の目安です。
1回目 7月10日
2回目 10月31日
3回目 翌年1月31日
また、概算保険料の申告書を提出した後、年度の途中で労働者が大幅に増え、賃金の増額が増加することがあります。したがって、保険料も増加するため、変更した額を申告・納付する必要があります。
届け先は先述のグループによって異なります。
労災保険・雇用保険を別々に申請する(二元適用事業)
→労働基準監督署とハローワークに届出
労災保険・雇用保険を同時に申請する(一元適用事業)
→労災保険分を労働基準監督署、雇用保険分を都道府県労働局に届出
ちなみに、労働保険料の「申告」を忘れたり、内容に誤りがあった場合には、政府が労働保険料の額を決定し、事業主宛に「通知書」を送ります。事業主は定められた期日までに社会保険料を納付しなければなりません。
また、「支払い」を忘れた場合には、まず督促状で納付期限が再指定されます。督促状の期日までに支払わなかった場合、延滞金が発生します。
さらに知りたい点・ご不明な点等がありましたら、下記までお気軽にお問合せください。
【受付】平日10:00~19:00
※「記事を見た」とお伝えいただくと、スムーズにご案内することができます。
※ご相談内容によっては、有料の労務相談に切り替える場合がございます。
電話 03-6272-6183
メール info@spot-s.jp
テキストテキスト
あああああ