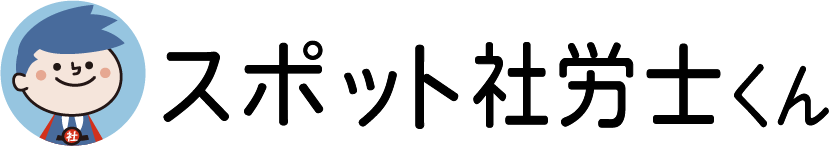基礎知識
2020.06.09
【社労士監修】70歳定年法とは?「改正高年齢者雇用安定法」の背景、年金や失業保険まで徹底解説
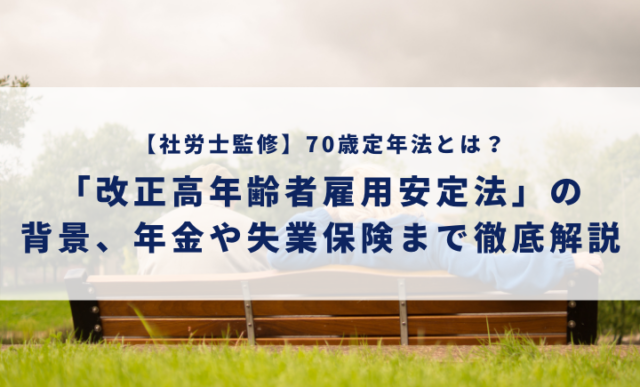
そもそも定年延長とは?再雇用とは?
2021年4月より、改正高年齢者雇用安定法によって、「70歳までの就業機会を確保すること」が事業主の努力義務とされます。
本題に入る前に、まずは、定年延長と再雇用の違いを整理しましょう。
定年延長の場合、今までの給料や働く時間を変更することなく、そのままの労働条件で働きます。いったん退職するという手続きをしないので、実際に会社を辞めるまで、退職金はもらえません。
一方、再雇用の場合は、労働者がいったん会社を退職します。そのタイミングで、退職金を受け取れます。その後、給料はいくらにするのか?労働時間は、何時間にするのか?など新しく労働条件を決めます。
このように、定年延長は、退職金をもらわずに今まで通り働き続ける一方で、再雇用は、退職金を受け取り、新しい労働条件で働きます。
定年延長と再雇用の違いを整理したところで、本題に入ります。
定年延長や再雇用についての法律は?
2013年4月から、高年齢者雇用安定法により、定年を60歳と定めている会社は、労働者を最低でも65歳までは継続雇用できるようルールを変更しないといけなくなりました。
この高年齢者雇用安定法には経過措置があります。
2020年6月現在では、雇用しなければいけない年齢は63歳までです。2022年4月から64歳までとなり、2025年4月から65歳までになります。
この法律で、定年退職の年齢を段階的に引き上げ、2025年からは企業が労働者を65歳まで雇用することを義務づけました。
しかし、今の日本の状況では「仕事からリタイアするのは65歳でもまだ早すぎる」ということになったのです。
そこで、企業に対して、労働者を雇用し続けなければならない上限の年齢をさらに引き上げるための法律ができました。
それが、改正高年齢者雇用安定法です。
2021年4月にスタートする改正高年齢者雇用安定法で、70歳までの雇用の継続や定年制度を廃止することなどが、企業の努力義務になったのです。
これが世間で言われている、「70歳定年法」です。
以下は、厚生労働省が出している「70歳定年法」の概要です。

70歳定年法ができた背景は?
改正高年齢者雇用安定法、いわゆる「70歳定年法」ができた背景は3つあります。
1つ目は、日本は、超高齢化社会であり、若い人が少なく労働力が不足しているということ
今まで働いていなかった年代の人に働いてもらうことによって、日本の経済活動を活性化していこうと考えているのです。
経済財政諮問会議によると、定年を70歳にした場合、国民の消費が4兆円増加するという試算があります。
2つ目は、高齢者の生活資金が不足してしまうということ
最近、老後は貯金が2,000万円必要であるとテレビ等のニュースで騒がれたことは記憶に新しいでしょう。
この2,000万円という金額は老後に必要な資金として正しい金額ではないかもしれません。しかし、今の日本では、年金だけでは老後の生活が苦しいことは間違いないと言っていいと思います。
現在の年金の受給開始年齢は、段階的に引き上がってきており、2025年には、年金の受給開始年齢は65歳になります。
さらに、年金の支給金額は減っていきます。
年金支給開始年齢が70歳になるという噂もあります(ただし、年金の支給開始年齢が70歳になるというのは、具体的に決まっている話ではなく、政府内には反対意見もあります)。
そのため、高齢者の生活は年金だけに頼ることができず、今後さらに大変になります。
国の財政は厳しく、高齢者の生活が苦しいから年金を増やす、ということはできません。
そのため、65歳を過ぎても働ける体力がある労働者には働いてもらい、「皆に良い生活を維持してもらいたい」ということなのです。
3つ目は、厚生年金や健康保険などの財政のために保険料を払える働き手を増やしたいということ
厚生年金と健康保険の保険料は、一定時間以上働けば70歳未満の労働者からは給料から天引きすることができます。そのため、65歳以上の人が働いてくれれば、厚生年金と健康保険の保険料が今より多く徴収できるのです。
少子高齢化で今後、社会保障の財源が足りなくなっていくので、今まで働いていなかった年代からも高齢者を支えてもらおうということです。
経済財政諮問会議によると、定年年齢を70歳にすると、社会保険料の収入が2兆円増加するというデータがあります。
「70歳定年法」の成立には、65歳以上の方に働いてもらい経済を活性化していきたい、生活のために働いてお金を稼いでもらいたい、そして厚生年金や健康保険などの財源を確保したい、という3つの背景があるのですね。
参考資料: 内閣府 経済財政諮問会議
今の職場でいつまで働ける?
では、実際に、今の職場ではいつまで働けるのでしょうか?
今現在、会社に義務付けられていることは2つあります。
1.定年は60歳以上にする。
2.定年が60歳の企業は、本人が希望すれば再雇用して63歳までは雇用しなければならない(2025年4月以降は65歳)
そして、今回の改正高年者雇用安定法で、2021年4月からは、70歳までの継続雇用が、企業の努力義務になりました。
政府は、今回の法改正をしたことで企業がどのように変わっていくかを見て、この70歳定年を義務化するかを決めると言っています。
そのため、今後10年以内に、70歳までの雇用が義務化される可能性が高いでしょう。
参考資料: 首相官邸 政策会議「全世代型社会保障検討会議中間報告」
70歳定年法は、だれが対象?
70歳定年法は、だれが対象なのでしょうか?
現在は、高年齢者雇用安定法で、希望者全員を65歳まで(2025年4月までは63歳まで)継続して雇用する義務があります。全労働者を対象とした仕組み作りが企業の義務なので、優秀な社員であるかどうかなどで企業が再雇用する労働者を選ぶことはできません。
2021年4月から始まる70歳定年法でも、希望者する労働者全員が対象になります。
ただし、現在は、70歳定年制度は企業の努力義務なので、希望者全員が70歳まで働けるかは、それぞれの会社次第になります。
役職定年は、どうなるのか?
70歳定年法により、役職定年はどうなるのでしょうか?
役職定年とは、管理職である社員が、ある年齢に達したときに管理職から外れ、一般の社員に戻る制度です。
企業にとっては、社員の人件費の抑制と若い人のために管理職のポストを空けられるというメリットがあります。
以下の人事院のデータを見てください。


この人事院のデータを見ると、役職定年の年齢で1番多いのは55歳です。そして、役職定年後の給料は、ほとんどの場合で下がります。
70歳定年法は、役職や雇用形態には関わらず一定年齢まで雇用を継続するように、としか定めていないので役職定年には影響しません。
70歳定年法ができても、役職定年の年齢があがることはないでしょう。55歳を過ぎたら給料が下がることを前提にライフプランを立てたほうが安心です。
定年延長や再雇用された場合の年金は?
定年延長や再雇用をされた場合の年金はどうなるのでしょうか?
65歳以上になっても会社員として働いていれば厚生年金の保険料を払うことになるというデメリットがあります。
しかし、厚生年金の保険料を払うので、年金額が上乗せされ、もらえる年金の額が増えるというメリットがあります。
また働いていて給料だけで十分暮らせるのであれば、年金を給付してもらう年齢をもう少し後にするという選択もできます。
年金を給付してもらう年齢を遅らせると、もらえる年金の額が増えます。
1か月単位で給付してもらえる年金の時期を遅らせることができ、現在は、最大で70歳まで遅らせられます。
このとき、遅らせた年金給付の時期に応じて、1か月当たり0.7%、最大42%、年金の受給額がアップします。
次に、年金をもらいながら65歳以降に働いて給料をもらうと、もらえる年金の額はどうなるのか見てみましょう。
もらえる年金の1か月当たりの額と、1か月当たりに貰う給料の合計が47万円を超えると、(超えた分の金額)×1/2の額が年金の給付金額から差し引かれます。
年金と給料の合計が、47万円を超えると損をしてしまうのです。

現在、年金をもらっている人の平均の年金額は1か月で、14万7千円くらいです。
以下が厚生年金の年金額のデータです。

平均的な年金額の人が、1か月当たりの給料を約32万円以上会社から貰えば、年金が減らされてしまうかもしれません。
また、給料を普通の人より多くもらっているという方であれば、もらう年金の額が高いので、この1か月当たりの給料がもっと低くても、年金の給付金額を減らされてしまうという事も起こります。
このように、65歳以上で働くと、まず給料から年金の保険料が引かれ、その分年金の給付額は増えていきます。
もし、1か月当たりの年金額と給料の合計が47万円を超えれば、その月は給付額が減ってしまいます。
年金額と給料の合計が47万円を超えなければ、働けるメリットは大きいでしょう。
定年延長や再雇用と雇用保険(失業保険)の関係は?
失業保険は、正式には雇用保険といいます。
定年延長や再雇用されて働いた後に仕事を辞めた場合、雇用保険はどうなるのでしょうか?
定年退職した後、新たに仕事を探す人には給付金が国から支給されます。この給付金を失業給付と言います。
仕事を辞めたときの年齢が65歳未満であるか、65歳以上であるかで給付金の額が変わります。
まず、仕事を辞めた年齢が65歳未満だった場合を見てみましょう。 本人の申請により失業給付の給付金(基本手当)を日額単位で受け取ることができます。
65歳未満の人であれば、一定の要件を満たすと、国からお金がもらえます。
この65歳未満の人で給付金をもらうための条件は3つあります。
1.退職する直前の2年間に、合計で12か月以上、雇用保険に入っていた。
2.すぐに働くことができる(健康上の問題や家庭の問題で、すぐに働けない場合は対象外)
3.積極的にハローワークに通って仕事を探している。この3つの条件を満たせば、国から給付金がもらえるのです。以下が会社に勤めた年数に応じて、給付金がもらえる日数です。

(基本手当日額)×(給付金がもらえる日数)が、最終的に国からもらえる上限額です。
給付金がもらえる日数が経過する前に、再就職が決まれば、そこで給付金の支給は終了です。
1日当たりの給付金の額はいくらでしょうか?
給付金の1日当たりの額は、その人のもらっていた給料の額と年齢によって違います。
まず、仕事を辞める前の直前の6か月の月給を平均します。それをもとに1日当たりの給料がいくらになるか計算します。
これが賃金日額です。
そして、この賃金日額に、給付率を掛けた金額が1日当たりの給付額になります。
この1日当たりの給付額を基本手当日額といいます。
以下は、厚生労働省が作っている基本手当を確認するための年齢別の早見表です。

なお、特別支給の老齢厚生年金を受給している場合、基本手当と両方を受給することはできません。雇用保険からの基本手当を受給している間は、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となります。
次に仕事を辞めたときの年齢が65歳以上の場合の給付金について見てみましょう。
仕事を辞めたときの年齢が65歳以上の場合、高年齢求職者給付金が受給できます。
先ほどと違い、この高年齢求職者給付金は、1年以上働いていた場合には50日分、1年未満しか働いていない場合は30日分、給付金をもらえます。
この2パターンしかありません。
さらに、高年齢求職者給付金は年金と同時に受け取れます。
年金が減らされることはありません。
65歳以上の場合は、給付金を受けるためのハローワークに通う等の条件はありません。
以上のように、仕事を辞めたときの年齢が65歳未満である場合と65歳以上である場合で給付金の額は変わりますが、仕事をしようとする意思と、仕事をできる環境があれば、いくつになっても国から給付金が出るのです。
「70歳定年法」について理解が進みました。まずは、現状義務づけられている65歳までの定年延長措置が確実に履行されているか、社内規程をいまいちど見直してみます。
オンラインセミナー(無料)のご案内

人事労務を学ぶと会社は強くなるをコンセプトに スポット社労士くんでは、「給与計算・助成金」といったテーマで場所や時間の制限なく無料で学べます。 労務の専門家の社労士が直接指導。全国から累計1万人が受講。 中小企業経営者に必要な知識である人事労務の基礎から、 給与計算、助成金、人材育成等に関するセミナーをそろえています。 直近のテーマ ・(給与計算)楽してミスしない「給与計算」仕組みのつくり方 ・(採用)人が採れない会社はなぜハローワークを活用しないのか? ・(助成金)みんなが喜ぶ助成金 ・(評価制度)小さな会社で人事評価はいるのか? ・(求人票)すごい求人票の書き方!激変したハローワークを使いこなす! ・(労働基準法)ココ重要!社長が知っておきたい労基法 オンラインセミナー詳細はこちら https://www.spot-seminar.com/
関連記事はこちら

「有料求人サイトに登録したものの、思ったように人材が集まらない…」 「せっかく入った人がすぐにやめてしまう…」 そんな悩みが「スカウトマン&サーベイ」ですべて解消されます。 【導入後メリット】 ・通年採用がコスト0円で実現できるようになる ・欲しい人材からの応募が増える ・会社の良いところ良くないところがわかり、強い会社づくりへ一歩踏み出せる ・採用後の労務相談も社労士が無料で対応