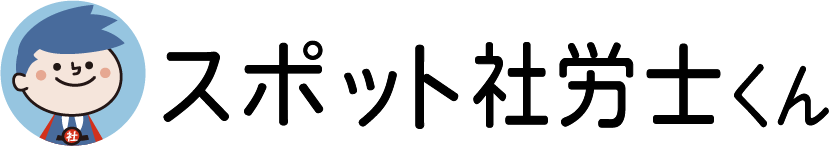社員の事
2020.05.23
会議では誰でも自由に発言して良いわけではない?心理的安全性にまつわるケーススタディ
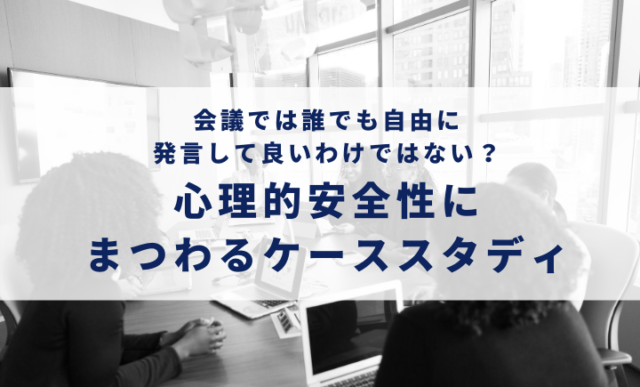
中途採用入社Aさんのケース
都内の中小企業に、28歳の中途採用社員、Aさんが入社してきました。
Aさんは前職では営業職の期待のエースとして働いていた、優秀な社員です。
今日は初めての社内会議への出席です。
Aさんは張り切っており、何か一言でも発言したいと意気込んでいます。
いよいよ会議が始まりました。
しばらくすると、Aさんが前職でも取り扱ってきたテーマがトピックとしてあがりました。Aさんはチャンスだと思い手を上げ、自分の意見を述べました。
すると、会議室に流れる、何とも言えない空気。上司と同僚の薄い反応。
Aさんは自身の発言に何か問題があったのではないかと、意気消沈してしまいました。
Aさんになにか問題があったのでしょうか?
すこし時間をおいてショックも和らいだ頃、Aさんは会議を振り返りました。すると、自身がまだ若く、かつ中途採用で入社から日も浅かった為、実は発言権がなかったのではないか、と考えました。
そのため、Aさんはそれ以後、会議へ参加する際にも発言をせず、ただ静かに座っているようになったのでした。
このようなケースは、Aさんの会社だけではなく、いたるところで見られる現象ではないでしょうか。
それは心理的安全性の問題でした
心理的安全性とは、ハーバード大学で組織行動学を研究する、エイミー・エドモンドソン氏の提唱する概念です。
「他人の反応を恐れたり羞恥心を感じる事なく、自身をつつみ隠さずオープンに出来るような職場の雰囲気」を指し、近年Google等、従業員のエンゲージメントの高い組織で見られる組織文化として注目されています。
今回のケースで言えば、例えば会議などで自由に発言しても受け入れられる、罰されないという権利を示します。
これは社内規定等に明示されているものではなく、組織の醸し出す空気(=組織文化)です。
例えば、心理的安全性の高い組織とそうではない組織を比較した際には、前者の方が社内における事務ミス等の報告件数が高まる傾向にあります。それは自身がミスの報告をしても罰されないという心理的安全性があるためです。
参考動画です。
Building a psychologically safe workplace / Amy Edmondson(心理的安全性のある職場を作るために / エイミー・エドモンドソン)
過去のインタビューでは、エドモンドソン氏は、組織にとって心理的安全性を作り、恐れのない状態を作ることの重要さについてこう述べています。

“「恐れ」には2つの種類があります。1つは健全な恐れ。納期を守れるだろうか、競合に勝てるだろうか、このレベルの品質を実現できるだろうかなど、チームが学習し、成長するためにも必要な恐れです。もう1つは、不健全な恐れ=人間関係に関わる恐れです。この恐れは「他人からどう思われているだろうか」を過剰に心配することから生じるもので、社員の行動に多大な悪影響を及ぼします。不健全な恐れがまん延した組織では、社員は畏縮し、新しいことを提案したり、リスクをとったりすることができません。”
ーNIKKEI STYLEより
ミスがあれば速やかに報告をされた方が良いということは、言うには及びません。
その為、組織ではこのような文化の醸成をする必要があるのです。
より良い職場にするヒントは?
では、より良い職場をつくる為に最も重要な事はなんでしょうか。エイミー・エドモンドソン氏は3点挙げています。
最も重要なのは職場において、職場において人々が持ちつ持たれつ、頼り合う必要があるのだということを明確にすることです。
加えて、人はミスを犯すという事実を受け入れることも重要です。
最後に、職場のメンバーの声に耳を傾けることが重要です。
そして再びAさんのケース
Aさんの直属の上司は、会議で発言をしなくなったAさんを心配し、「今度の会議ではAさんの意見も聞いてみたいな。」と発破をかけました。Aさんに比較的年齢の近い先輩も元気のないAさんを心配し、「そういえばこの間の会議で発言していた件、詳しく教えてよ。」と声をかけました。
Aさんはこの2人の声かけにより、再び会議で発言をすることができるようになったのでした。
Aさんの所属している組織は、Aさんに近しい上司と先輩を除き、たまたま心理的安全性の概念の希薄な組織でした。その為、Aさんのみならず、社員が萎縮する傾向にありました。
Aさんのようにやる気のある従業員が萎縮してしまわない為にも、心理的安全性を保った組織文化の醸成が重要になってきます。
Aさんのケースをふまえて、いま一度、自社の職場の雰囲気がどのようなものとなっているか、見直してみてはいかがでしょうか。