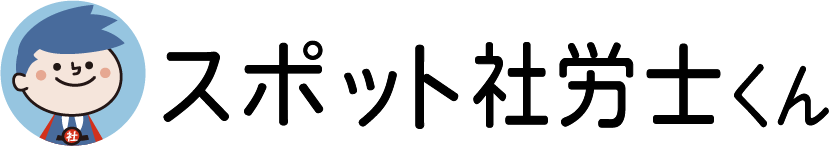テレワーク
2020.05.18
中小企業の在宅勤務・リモートワークのメリットとデメリット

コロナ禍で人々の働き方が変容しています。
対人接触を避ける為に通勤の自粛を求める企業が増えていますが、とくに中小企業の場合、これまで在宅勤務・リモートワークを活用していなかったために、通勤の自粛と同時並行で、制度導入を検討せざるを得ないケースが多く、現在、制度についての関心が一気に高まっています。
中小企業のリモートワーク導入率は低い
2019年8月に実施されたエン・ジャパンの調査によると、従業員数300人未満の中小企業における在宅勤務・リモートワーク導入率は14%でした。(有効回答社数491社)
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2019/18689.html
中小企業の「テレワーク」実態調査 ―『人事のミカタ』アンケート( エン・ジャパン)
コロナ禍での2020年4月においても、東京商工リサーチによる調査では、中小企業(従業員数非公開)の在宅勤務・リモートワーク導入率は20%に留まっています。(有効回答社数17,896社)
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20200410_03.html
第3回「新型コロナウイルスに関するアンケート」調査(東京商工リサーチ)
このように在宅勤務・リモートワークが注目され始めているとはいえ、未だ8割の中小企業が、導入には至ってはいません。
本記事では、在宅勤務・リモートワークにおける、社員への心理的な影響という観点を軸に、メリット・デメリットを整理してみましょう。
制度導入による影響を最も大きく受けるのは社員であり、社員にとって有効な制度でなければ、導入をしても長続きしないためです。
まずは、メリットから考えてみます。
(1)在宅勤務・リモートワーク導入におけるメリット
a)勤務形態に多様性が生まれる事で、社員の心理的安全性につながる
例えば介護や、保育園・幼稚園の終業後に年少の子供の預け先がない、などといった特別な事情により、時短勤務を余儀なくされる社員がいます。そうした社員は制度導入によって、必要に応じて、社外で業務に従事することができます。業務のブランクが生じなくなることで、同僚に対して引け目を感じることや、昇進・昇格への影響などといった不安を感じることが少なくなり、より心理的安全性を感じながら働くことが可能となります。
b)社員のエンゲージメントの高さにつながる
特別な事情のない社員についても、私用や、近年従事者が増加傾向にある副業などにより、在宅勤務・リモートワークが効率的である場合は、積極的に選択する事ができます。働き方の柔軟さを求める社員に対して、企業に対するエンゲージメントを高める結果につながります。
c)自分専用の環境の整備によって生産性が高まり、モチベーションが維持できる
職場にいると、他の社員や上司から不要不急の事で話しかけられる等、集中力が途切れることがあります。しかし自宅で働くにあたっては、そうした集中を妨げる要素が少なくなります。また、自宅の環境を職場として自分の働きやすいように作り変えることもでき、これによって生産性を高めることができます。結果的に、モチベーションの高い状態を維持することにつながります。
a)〜c)はすべて在宅勤務・リモートワーク制度をただ導入するのみではなく、運用体制を整備し、かつそれが有効に機能していることが前提です。
次にデメリットにも目を向けましょう。
(2)在宅勤務・リモートワーク導入におけるデメリット
d)これまでの働き方が通用しなくなり、不安感が醸成される
例えば、通勤勤務をしていた際には、会議で発言しないことが許容されていた側面があった一方、リモートでのオンライン会議では、発言しなければ出席していないものとみなされてしまう、等といったような不安感が醸成されます。
企業は、制度の導入によってこれまでの働き方が変容するということを社員へ周知徹底するとともに、対応策を検討して社員に示す必要があります。例えば、会議前に議題をあらかじめ共有し、テキストで意見を出すことを宿題とする、などの対応を取ることで、社員自身のやるべきことが明確になり、不安感が軽減されます。
e)1人時間が増える事により、孤独感が生じる
特に独身で一人暮らしの社員は、1日の中でほとんど誰とも会話しなくなることが考えられます。また、オンラインでテキスト等を用いて会話をしたとしても、それは人間的な温かみのない無機質な会話であり、社員の孤独感を軽減することには必ずしもつながりません。
孤独感を放置すると、心理的な不安感につながり、仕事への負の影響があります。対応策としては、オンラインで参加可能な部活動を取り入れたり、slackなどのコミュニケーションツールを導入することで、各人のペースで適宜雑談ができるような環境の整備が必要となります。
f)生活習慣が乱れ、メンタル不全につながる
特に独身で一人暮らしの社員は、起床時間・就寝時間共に遅くなる傾向があります。また三食きちんと摂らずに仕事にあたる可能性も考えられます。生活習慣の乱れは自律神経の乱れにつながり、それはそのままメンタル不全につながります。
起床してすぐ身だしなみを整える、自分なりの生活・仕事のルーティーンをつくる、三食きちんと摂るなど、会社の側で、ガイドラインを作成し、提供することが望ましいです。
以上、中小企業における在宅勤務・リモートワーク導入の是非を社員の心理面から考えました。
制度導入にあたっては、メリット・デメリットをふまえた上で検討を行うことが必要です。
アーカイブ
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月