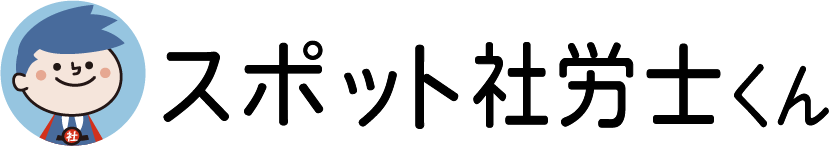基礎知識
2020.07.18
パートの働き方は?社会保険、扶養の壁、法定福利費の関係も徹底解説!

パートを募集していますが、パートも社会保険に加入させないといけないのですか?
面接で「扶養内で働きたい」と希望してきた応募者がいたのですが、どういう意味ですか?
パートでも要件をみたせば社会保険に加入しなければなりません。雇用契約書の労働時間などから判断します。
また「扶養内で働く」というのは社会保険の扶養内と税金の扶養内で基準がちがいますから、どちらか確認したほうがいいですね。
確認しやすいようにパートの社会保険の加入条件と扶養についてご説明しますね!
パートやアルバイトなどの短時間勤務者のなかには「扶養内で働く」ことを希望する人がいます。扶養には「社会保険の扶養」と「税金の扶養」があり混同されがちです。違いについて確認していきましょう。
パートの社会保険
パートの収入が一定以下であれば配偶者の被扶養者になることができ、健康保険・厚生年金にパート自身が加入して保険料を納める必要がありません。
社会保険の被扶養者になる年収要件は、
・年間収入が130万円未満
・60歳以上又は障害者の場合は、年間収入が180万円未満
一方で、パート自身の雇用契約書の労働時間によってはパート自身が社会保険に加入しなければならないことがあります。いわゆる「4分の3基準」と呼ばれるものです。
4分の3基準は1週間の所定労働時間および1ヵ月間の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であれば社会保険に加入しなければならないルールのことです。
所定労働時間を1ヵ月単位で決めている場合は次の計算式により判断します。
1カ月の所定労働時間×12ヵ月÷52週間 > 常時雇用者の4分の3
1週間の所定労働時間を算出して常時雇用者の4分の3以上であれば社会保険に加入しなければなりません。

上記の基準に関わらず、特定適用事業所では①~④をすべて満たせば社会保険の加入対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
③報酬の月額が8万8千円以上であること
④学生でないこと
この企業規模による特定適用事業所の要件は今後変わっていきます。
2020年6月に公布された年金制度改正法で社会保険の加入対象者を拡大することが発表されました。今後は 常時雇用者 500人以上となっていた企業規模が段階的に引き下げられます。
・2022年10月: 常時雇用者 100人超規模の企業まで適用
・2024年10月: 常時雇用者 50人超規模の企業まで適用
同時に雇用期間も2022年10月から、現状の1年見込みから「2ヶ月超」へ変更されます。
現在の加入条件と今後変更させる条件をまとめると次のようになります。

労働時間や給与、会社の規模によって社会保険の加入対象が違うのですね・・・雇用契約を結ぶ前に確認します。
会社側も影響を受けることがありますか?
パートが社会保険に加入するということは法定福利費が発生しますから会社の経費が増えます。
法定福利費の増加額について確認しましょう!
パートが社会保険に加入したときの法定福利費は?
パートが社会保険に加入すると保険料は本人と会社で折半します。本人負担分は給与引きします。会社負担分は法定福利費として経費になります。会社が給与引きした本人分と会社負担分を合わせて納付するシステムです。
仮にパートを雇用したとします。東京都の最低賃金1,013円で週30時間・月120時間勤務の雇用契約を結び勤務したとすると1カ月の給与は121,560円、交通費なしなら標準報酬月額118,000円です。法定福利費を計算してみます。
パートの年齢が40歳以上ですと介護保険料が必要になりますので、法定福利費は次のようになります。

※所得税についての言及は必要ないかと思います。代わりに、「※健康保険料率は協会けんぽ東京支部の料率を使用」と記載されるべきかと思います。
東京都の最低賃金で週30時間のパートを雇うと給与以外に以下の法定福利費が経費として発生することを認識しておきましょう。
40歳未満:月額法定福利費18,138×12カ月=年額法定福利費217,656円
40歳以上:月額法定福利費19,194×12カ月=年額法定福利費230,328円
法定福利費が発生するのは新規にパートを雇用する場合だけではありません。ご説明したように社会保険の特定適用事業所の要件は2024年10月までに段階的に引き下げられます。今と同じパートを雇用しているだけでも法定福利費が増加することもあるのです。
例えば社員数60名の会社で内パート10名は1日7時間週4勤務の雇用契約だとします。1週間の所定労働時間は28時間・月間標準所定労働時間は112時間です。仮に時給1,085円ですと1カ月の給与は121,560円となり標準報酬月額は上の例と同じです。
2020年現在は「4分の3基準」と特定適用事業所の要件から社会保険の対象外ですが、2024年になると会社が特定適用事業所の要件を満たすため1週間の所定労働時間が20時間以上のパート10名は社会保険の加入対象となります。
その場合の40歳未満の1名当たりの法定福利費は18,138円となり10名ですと月額181,380円です。
パート10名がすべて同じ年だと仮定して年間額を計算すると次のようになります。
40歳未満:月額法定福利費181,380×12カ月=年額法定福利費2,176,560円
40歳以上:月額法定福利費191,940×12カ月=年額法定福利費2,303,280円
(どちらも10人分)
あまりの金額の大きさに驚かれたのではないでしょうか。
法定福利費が増えるということは経費負担が増え、利益が減るということです。これだけ大きな数字ですと会社の経営にも影響してきます。
このように制度変更により会社が負担する費用が増加することがあります。制度の制定や改定の情報にはアンテナをはって対応するように気を付けましょう!
税扶養とは
税金の扶養内とはパートの年収が「パートの配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる基準内」であることをいいます。
配偶者控除とは、納税者に対象となる配偶者がいる場合に、納税者の所得税の計算のもととなる課税対象額から一定の金額の所得控除が受けられるというものです。簡単にいうと配偶者の所得税を減らします。
税扶養の条件は所得48万以下。収入で考えると103万円です。次の計算式で算出します。
所得48万以下+給与所得控除55万=103万
所得は38万円なのでは?と思われた方もいると思いますが、所得税は2020年に大きな改正がありました。
① 2020年分から基礎控除の改正38万円が48万円に増額
② 給与所得控除の最低額は65万円から55万円となり10万円減額。
①②の変更により、2020年度から配偶者控除は「年間の合計所得金額が48万円以下であること」に変更となりました。同時に給与所得控除が55万に下がるので給与収入の要件は103万円のままです。
パートの配偶者が所得控除を受けられる金額はパートの所得と配偶者の収入により下の図のようになります。
図の配偶者とはパートのことで、納税者本人はパートの配偶者をさします。

配偶者特別控除は一定額を超えた場合にまったく控除を受けられるのでなく、配偶者であるパートの収入により段階的に控除額が減らわれるものです。
下の図の配偶者の年収はパートの年収を指します。

気を付けたいのはパートの収入103万円を超えているのに配偶者の扶養をはずす手続きをしなかった場合です。
手続きをしていないので配偶者の年末調整が正しく行われません。確定申告で修正をしないと11月頃に税務署から所得税是正の案内がパートの配偶者の会社に届きます。
源泉所得税の手続きは会社の義務ですので、正しく処理されていないと会社が対応を求められるのです。
この場合は正しい所得税を計算しなおして不足分の所得税を会社経由で納付します。過去3年分が調査対象となり、市町村で所得証明書を取得するなど対応が大変ですので忘れずに手続きしましょう。
最近は学生アルバイトが扶養の上限103万を超える収入を得ている場合があり、所得税の是正の原因となっている例を多くみます。
学生アルバイトには税扶養の知識がないことが多いので雇入れ時に説明すると親切ですね。
扶養の壁とは?まとめて確認しましょう!
パートで働く短時間労働者は税扶養や社会保険の扶養条件を気にしています。○○の壁といわれるものを確認しておきましょう。
●100万の壁(住民税)
住民税にも基礎控除があり金額は43万円。所得税の基礎控除とは金額が違うので注意しましょう。会社員の住民税は「 基礎控除43万円 + 給与所得控除55万円=98万円」以上が課税対象です。
しかし住民税の均等割と所得割のいずれも課税されない対象の判断に「前年中の合計所得金額が45万円以下」との条件がありますから、実際には「給与所得控除55万円+非課税控除額45万円=100万円」を超えなければ課税されないということになります。
● 103万の壁(所得税)
配偶者に扶養されていると認識されるラインです。
基礎控除48万+給与所得者控除55万=103万
これを超えるとパートが自分で年間収入に係る所得税を納付することになります。
● 106万の壁(社会保険)
一定規模の特定適用事業所の健康保険と厚生年金の加入条件ラインです。
収入月88,000円以上×12カ月=1,056,000円 ⇒ 106万と認識されています。
現在の特定適用事業所の基準は「常時雇用者500人を超える」です。2024年10月までに段階的に引き下げられます。
● 130万の壁(社会保険)
配偶者の扶養に入り国民年金の第3号被保険者となれる上限ラインです。20歳以上60歳未満が対象です。
これを超えるとパートが自分で健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。

● 150万の壁(所得税)
配偶者の扶養から外れ控除が段階的に減額されるスタートラインです。
配偶者の所得税計算において扶養控除38万円が満額うけられなくなるラインです。配偶者の税負担が増えます。
● 201万の壁(所得税)
配偶者の扶養からはずれ控除が完全になくなるラインです。配偶者はパートに関する扶養控除をまったくうけられません。配偶者の税負担が増えます。

パートにはこんなに壁があるんですね・・・法定福利費も増えることがよくわかりました。
雇用契約を結ぶ時の条件掲示の参考にします。
雇用契約の条件次第で会社の法定福利費が増えるだけでなくパート本人も社会保険料や所得税の負担が増え、いわゆる働き損になる可能性がありますので雇用契約については労使で話し合ったほうがよいですね。
★オンラインセミナー(無料)のご案内

人事労務を学ぶと会社は強くなるをコンセプトに スポット社労士くんでは、「給与計算・助成金」といったテーマで場所や時間の制限なく無料で学べます。 労務の専門家の社労士が直接指導。全国から累計1万人が受講。 中小企業経営者に必要な知識である人事労務の基礎から、 給与計算、助成金、人材育成等に関するセミナーをそろえています。 直近のテーマ ・(給与計算)楽してミスしない「給与計算」仕組みのつくり方 ・(採用)人が採れない会社はなぜハローワークを活用しないのか? ・(助成金)みんなが喜ぶ助成金 ・(評価制度)小さな会社で人事評価はいるのか? ・(求人票)すごい求人票の書き方!激変したハローワークを使いこなす! ・(労働基準法)ココ重要!社長が知っておきたい労基法 オンラインセミナー詳細はこちら https://www.spot-seminar.com/ ****************************************************** スポット社労士くん社会保険労務士法人 TEL 03-6272-6183 / FAX 03-6701-7312 セミナー担当:田辺、細田、越智 メール info@spot-s.jp ホームページ http://www.spot-s.jp
おすすめ記事

「有料求人サイトに登録したものの、思ったように人材が集まらない…」 「せっかく入った人がすぐにやめてしまう…」 そんな悩みが「スカウトマン&サーベイ」ですべて解消されます。 【導入後メリット】 ・通年採用がコスト0円で実現できるようになる ・欲しい人材からの応募が増える ・会社の良いところ良くないところがわかり、強い会社づくりへ一歩踏み出せる ・採用後の労務相談も社労士が無料で対応