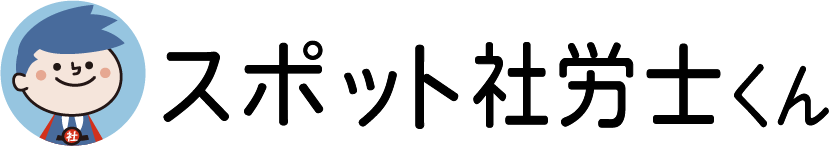NEWS
2020.06.22
「雇用とは、業務委託とは」シリーズ① 基礎編
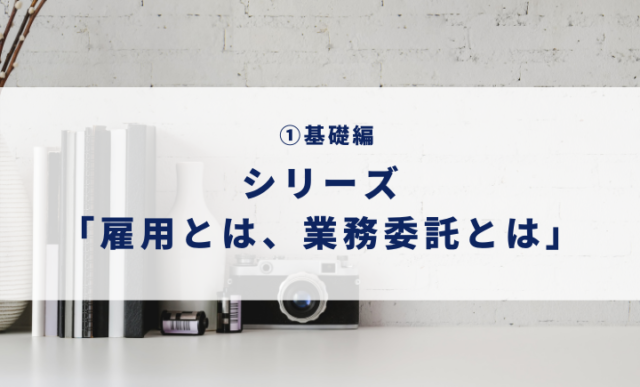
「雇用と業務委託」は、「仕事を依頼する会社などの組織」と「実際に仕事をする働く人」がいる点では同じですが、法律上はかなり異なります。
そして、雇用のメリット・デメリットと、業務委託のメリット・デメリットは、会社と働く人でまったく異なります。
本シリーズでは、雇用とは何か、業務委託とは何か、について3回にわけて解説していきます。
初回は「基礎知識」編です。
例えば、同じ企業で同じ仕事をして同額のお金を得ても、雇用されている人は労働者で、業務委託を受けている人は個人事業主と呼ばれます。このような「そもそもの違い」を整理してみましょう。
雇用とは
まずは雇用について解説します。
雇用には次のような特徴があります(*1)。
・使用者と労働者が雇用契約を結ぶ
・労働者は使用者に使用(雇用)される
・労働者は労働を使用者に提供する
・使用者は労働者に賃金を支払う
この4項目の内容に触れる前に、専門用語を解説します。
使用者とは、「会社」「経営者」「社長」「CEO」などのことです。
労働者とは、「働く人」の一種です。「正社員」や「契約社員」「パートタイム」は労働者です。
雇用契約(労働契約)とは、民法や労働関係の法律で定められている契約の一種です。
雇用契約を結ぶと、労働者は使用者に「使用(雇用)」されます。雇用されている間は、労働者は使用者の指示にしたがって働かなければなりません。
労働とは、「働くこと」や「仕事をこなすこと」です。
賃金とは、「労働の対価」であり、対価は主に「お金」です。
雇用契約の範囲内で「働いてもらう」「働く」
雇用の特徴の4項目のなかで最も重要なのは「雇用契約」と「労働と賃金の交換」です。
そもそも「契約」とは、「こうしてくれれば、こうします」という内容を決めた約束です。
したがって雇用契約とは、「この労働をしてくれれば、これだけの賃金を支払います」という約束である、といえます。
会社と労働者の間で雇用契約が結ばれると、労働者は働き、会社(使用者)は働きに見合った賃金を支払います。そのため、労働(働き)と賃金が交換されたように見えます。
なぜ雇用するのか、なぜ雇用されるのか
ここまでの説明で「なぜ、労働と賃金の交換だけで終わらないのか。会社はなぜ労働者を雇用し、労働者はなぜ会社に雇用されるのか」という疑問が湧くと思います。
雇用契約を結んでまで「雇用して」「雇用される」のは、そのようにしないと不安定だからです。
会社の社長の立場になって考えてみます。
労働者に労働を依頼したものの、約束の時間に現れなかったら、労働してもらえません。これでは不安定です。
そこで、雇用契約書のなかで、「午前9時から午後5時までに会社にいて、働くように」という内容を盛り込んでおくわけです。このように約束しておけば、労働者は朝9時に会社に現れて、夕方の5時まで労働します。これで会社の社長は安定します。
次に、労働者の立場になって考えてみます。
労働者が仕事を終えたとき、社長がその出来栄えに満足せず、「当初1万円を支払うと約束していたが、この出来栄えでは5千円しか支払えない」と言ったら、労働者は安定しません。
そこで、雇用契約書に「午前9時から午後5時まで働いたら、1万円の賃金が発生する」という内容を盛り込みます。これで労働者は安定します。
さらに雇用契約書に「一度採用したら、65歳まで働くことができる」と書いておけば、労働者はさらに安定します。
「なぜ雇用するのか、なぜ雇用されるのか」
それは、会社、社長、労働者が安定するためなのです。
業務委託とは
雇用が、会社と社長と労働者に安定をもたらすのであれば、「働かせる形と働く形」は雇用だけで十分なはずです。
雇用以外に「業務委託」という形態があるのは、雇用では不便なことが起きるからです。
業務委託は雇用の不便さを解消する
雇用は、会社・社長にとっても、労働者にとっても不便になることがあります。
雇用した労働者が、きちんと午前9時から午後5時まで働いているものの、まったく仕事ができなかったとします。それでも雇用契約を結んでいるので、社長は簡単には雇用をストップすることができません(簡単に解雇することはできません)。これが社長にとっての雇用の不便さです。
では、雇用された労働者が、ものすごくよい業績をあげて、会社に1億円の利益をもたらしたらいかがでしょうか。それでも雇用契約で、賃金の額を1日1万円と決めていたら、労働者はそれしかもらえません。これが労働者にとっての雇用の不便さです。
業務委託にすれば、社長も労働者も、雇用が生む不便さを解消することができます。
業務委託で働く人は「労働者」ではない
会社が業務委託契約を結んで仕事を行わせるとき、仕事を行う人(「個人事業主」)は、雇用契約を結ぶ「労働者」とは異なる取り扱いを受けます。
業務委託の特徴は次のとおりです(*2)。
・注文主(会社や社長など)が個人事業主に仕事を委託する
・注文主と個人事業主が業務委託契約を結ぶ
・個人事業主がその仕事を完成させる
・注文主は個人事業主に報酬を支払う
業務委託では、会社や社長は「使用者」ではなく「注文主」になっている点に注意してください。また、注文主が支払うお金も「賃金」ではなく「報酬」です。
このように用語を使いわけることによって、業務委託を雇用と区別しているわけです。
指揮命令を受けない
業務委託では、個人事業主(業務を行う人)は、注文主(会社や社長)の指揮命令を受けません。
注文主は個人事業主に「この仕事を、この日までに完成させたら、○円を支払います」と言うだけです。個人事業主は原則、何時間かけても、どこで働いても、どのような方法を使っても構いません。
ただ、業務の内容によっては、注文主の指揮命令が「まったくのゼロ」では立ち行かないことがあります。その場合、多少は、注文主が指揮したり、個人事業主に命令したりします。
しかし、指揮命令が強くなりすぎると、雇用と見分けがつかなくなります。
指揮命令がまったくないか、または限りなく小さいことが、「業務委託を業務委託たらしめている」といえます。
会社にとっての「雇用と業務委託」のメリット・デメリット
雇用は会社・社長に、メリットもデメリットももたらします。
また、業務委託も会社・社長に、メリットもデメリットももたらします。
それぞれのメリットやデメリットは多数ありますが、代表的なものを紹介します。

社長にとって、労働者を雇用するメリットは、優秀な労働者を「囲い込める」ことでしょう。優秀な労働者に安定して働いてもらえれば、自社が儲かるだけでなく、ライバル会社より有利になります。
しかし雇用には雇用コストがかかります。例えば、会社が仕事を確保できないと労働者を遊ばせることになりますが、それでも社長は、労働者に賃金を支払い続けなければなりません。もし仕事を確保できないという理由で簡単に労働者を解雇したら、社会から非難されるでしょう。
さらに、労働者を雇用するには、さまざまな社会保険をかけなければならず、会社は保険料を負担しなければなりません。
業務委託にすれば、雇用コストを省くことができます。
しかし業務委託では、仕事が終わったら契約が終了するので、優秀な働き手が別の会社に行ってしまうかもしれません。
優秀な個人事業主を確保し続けるには、やはりそれなりの高額な報酬を支払う必要があります。その結果「雇用したほうがコストがかからなかった」という結果になることもあります。
働く人にとっての「雇用と業務委託」のメリット・デメリット
続いて、働く人(労働者または個人事業主)にとっての、「雇用と業務委託」のメリットとデメリットをみていきます。

日本では、働く人のほとんどは、労働者です。
総務省によると、従業者数(≒働く人=労働者+個人事業主)5,349万人のうち、個人企業(≒個人事業主)は11.9%に過ぎません。88.1%は労働者です(*3)。
なぜ労働者が多いのかというと、日本の労働環境が、世界的にみても安定しているからです。もちろん、労働環境にもさまざまな問題がありますが、それでもなお、労働者でいることは、労働者に大きなメリットをもたらします。
例えば、会社は、労働者を簡単に解雇できません。「仕事ができないから」という理由だけでは、解雇できません。
簡単に解雇されないので、労働者はじっくりスキルを高めていくことができます。会社の売上高に貢献できない時期があっても、いずれ挽回することができます。
雇用が持つ安定感は、労働者にとって大きな魅力でしょう。
また、労働者にはさまざまな社会保険がかけられていますが、その保険料の大半は会社が負担します。これは賃金に勝るとも劣らない「金銭上の得」です。
業務委託を受けている個人事業主は、自分で保険料を支払って社会保険に加入する必要があります。
さらに業務委託では、仕事が終了したら会社との関係がいったん途切れてしまいます。個人事業主は常に「次の仕事」を探し続けなければなりません。
そして注文主は、「仕事ができないから」という理由で、個人事業主への発注を止めることができます。とても不安定です。
「次の仕事」を取り続けるには、個人事業主は自分の力で、そして自分のお金でスキルを高めていかなければなりません。
ただ、業務委託の報酬は、個人事業主と注文主(会社・社長)の話し合いで決めることができます。注文主に実力を認めてもらえば、報酬の額はいくらでも跳ね上がります。
業務委託契約の内容に満足できなければ、個人事業主は注文主の業務委託を拒否することができます。
まとめ~何を求めるかによる
雇用も業務委託も、メリットの総量とデメリットの総量は、ほとんど同じと考えてよいでしょう。ただ、それぞれの人が置かれている状況によって、メリットの量とデメリットの量が変わってきます。
経営者も働く人も、「雇用と業務委託では、どちらのほうが自分のメリットを最大化できるか」という視点で、働かせ方や働き方を考えてみてください。
*1:雇用契約と労働契約 – 日本労働研究雑誌
*2:さまざまな雇用形態|厚生労働省
*3:統計局ホームページ/統計Today No.82
○「雇用とは、業務委託とは」シリーズ