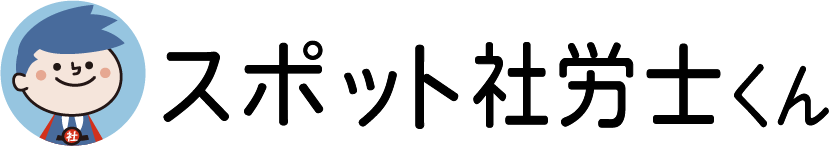テレワーク
2020.09.10
テレワーク先進国アメリカに何を学べるのか?

テレワークとは、労働者が、勤務先の事務所以外の場所で仕事をする業務形態のことです。
テレワークの概念は、1970年代のアメリカに存在しました。
新型コロナウイルスの感染拡大(以下、コロナ禍)で、日本でもテレワークが拡大しています(*1)。
日本では以前から「テレワークは便利そうだ」という雰囲気はありましたが、本格的に普及したきっかけは、間違いなくコロナ禍です。
コロナとの共存が避けられないウィズコロナ社会ではテレワークの推進または継続が避けられないので、本場アメリカのテレワークを学ぶことは、意味があります。
*1:https://www.nikkei-r.co.jp/column/id=7211
テレワークの始まりは1973年のNASA
アメリカの物理学者ジャック・ナイル氏は1973年に、米航空宇宙局(NASA)からの依頼で通信システムを構築していました(*2)。ナイル氏はこの仕事を自宅で行ない、そのスタイルを「テレコミューティング(telecommuting)」と呼びました。テレコミューティングは「在宅勤務」と訳され、これが現代のテレワークの起源とされています。
その後アメリカは、オイルショックや大気汚染といった環境問題に悩まされます。そこで政府関係者に、エネルギー使用量が少ないテレワークが推奨されるようになりました。さらに2000年代にITとネットが驚異的な進化を遂げたことで、テレワーク環境が整うようになりました。
*2:https://www.ipa.go.jp/files/000083543.pdf
アメリカ人に向いた働き方
テレワークはアメリカ人に向いた働き方といえます。アメリカ人は一般的に独立心が旺盛で、個人で業務を進めることを嫌いません。また、アメリカの企業は一般的に、労働者に努力や過程よりも結果を求めます。
テレワークでは、自宅の部屋に閉じこもって仕事をすることになるので、個の力が必要になります。
さらに、上司が部下の仕事の過程に無関心であれば、部下は仕事を自宅で仕上げてインターネットで上司に送ることができます。
そして、アメリカ人の合理主義も、テレワークの特徴とマッチします。
「通勤」は、会社の仕事をするために人の体を交通機関で動かす作業です。人を動かさずに会社の仕事ができるのであれば、人は時間や労力を使わないで済みますし、交通機関に使うエネルギーも節約できます。
会社に行かなくても仕事ができるなら、テレワークをやらない理由はないといえます。
そこにコロナ禍が起こり、テレワークへの評価はさらに高まりました。
ツイッター社は2020年5月、希望者に無期限でテレワークを認めることを決め、フェイスブックもそれに追随しました。
今のアメリカのテレワーク事情と課題
ジェトロ(日本貿易振興機構)によると、コロナ禍前の2019年のアメリカのテレワーク環境は次のような状態でした(*2)。
・テレワークで業務を行える労働者は就業者全体の7%ほど
・テレワークが普及している業種は、企業幹部、IT管理者、財務アナリスト、会計士、弁護士、ソフトウェア関係者など
・テレワークが不可能な業種は、レストランの給仕、美容師、配管工、警察官、建設労働者など
それがコロナ禍によって次のように変化しました。
・テレワークを行ったことがある就労者の割合は、2020年3月13日には31%だったが、4月20日には63%に倍増した
コロナ禍は他人との接近によって拡大するので、他人との接触を回避できるテレワークはうってつけといえます。
アメリカ人はテレワークのメリットをどのように考えているのか
2020年4月にアメリカで行なわれた調査では、テレワークのメリットとして次の項目が挙がりました(*2)。
・通勤しなくてよい:47%
・スケジュールが柔軟になる:43%
・正装しないでよい:33%
通勤しないことでプライベートの時間が増え、それがワークライフバランスを向上させられる点も評価されています。
デメリットも小さくない
ただ、アメリカ人はテレワークにデメリットも感じていて、次のような意見が目立ちました。
・共同作業が困難:33%
・作業を中断させられることが多い:27%
・オフィスでのルーティン作業を維持できない:26%
そしてそのデメリットは必ずしも小さくなく、遠隔での勤務を好む人が40%だったのに対し、オフィスでの勤務を好む人は39%と拮抗しています。
共同作業の困難さは「テレワークの壁」といえます。
テレワークの壁「共同作業の困難さ」をどう克服するか
共同作業の困難さを解決するツールも、アメリカで誕生しています。
その代表例はZOOMでしょう。
ZOOMには、無料版でも3人以上の会議を40分利用できる、参加だけならログインすら要らない、スマホにも対応する、といった利便性があります。
ZOOMのユーザー数は、コロナ禍前の2019年12月の1,000万人から、2020年3月には2億人以上になりました。わずか3カ月間で20倍以上になりました。
アメリカではさらに、通信大手のヴェリゾン社が2020年4月に、ハイクオリティ・ビデオ会議システムを開発したブルージーンズ・ネットワーク社を買収したことが話題になりました。
ブルージーンズ社のビデオ会議システムは、ビジネスでの利用を前提とした有料版のみの設定で、遠隔医療、オンライン学習、現場作業サポートなどに使うことを想定しています。
IT大国アメリカは、ITでテレワークの壁を越えようとしています。
日本はまだテレワークの拡大の余地がある
冒頭で、日本でもテレワークが拡大していると紹介しましたが、アメリカの普及率(2020年4月20日、63%)に比べると見劣りするものがあります。
総務省の「情報通信白書」によると、2018年のテレワーク導入率は19.3%でした。
しかし2020年4月になっても、パーソル総合研究所の調べでは27.9%、楽天インサイトの調べでも34.3%にすぎません(*3)。
日米では統計手法も普及率の定義も異なるので、単純にコロナ後の日本での普及率はアメリカの半分であると断定することはできませんが、日本のマスコミがあれほどテレワークで賑わっていた割には、日本企業のテレワーク化は進んでいないようです。
ただ、日本でもコロナ禍の前後でテレワークが増えているので、密回避の対策として評価されていることは間違いありません。
ではなぜ日本では、テレワークは少し増えた程度にとどまっているのでしょうか。
*3:https://www.newsweekjapan.jp/kim_m/2020/07/post-19.php
日本人はテレワークが苦手か
コロナ禍にあっても日本でテレワークが爆発的に増えなかったのは、働き方が関係しているのではないか、という指摘があります(*3)。
日米では、雇用方法が大きく違います。日本はメンバーシップ型、アメリカはジョブ型といわれています。
メンバーシップ型雇用とは、職務を限定せず採用し、OJTや社内研修で人材育成をする方法です。
ジョブ型雇用では、職務内容を明示して、その職務に適した人を採用し、その人にその職務をさせます。
そのため日本企業では、社員の会社への帰属意識が強くなりやすくなりますが、アメリカ企業の社員たちは、仕事への帰属意識が高くなりやすくなります。
会社を愛する日本人労働者にとって、会社の事務所に行くことは苦ではありません。もちろん、通勤ラッシュを苦に感じる人は多くいますが、「会社に行かなくてよいテレワーク」に強い魅力を感じない人は、アメリカ人よりも多くなります。
また、ジョブ型雇用では、若い社員は先輩や上司に教わりながら仕事を進めることになります。「コミュニケーション濃度」が薄まるテレワークは、教わるほうも教えるほうも不都合を感じるでしょう。
アメリカの労働者と比べると、日本の労働者はテレワークが苦手といえそうです。
業務のテレワーク化が遅れている
総務省の通信利用動向調査(2019年)によると、テレワークを導入していない企業の71.3%が「テレワークに適した仕事がないから」という理由を挙げていました(*4)。
確かにアメリカでも、レストランの給仕、美容師、配管工、警察官、建設労働といった仕事では、テレワーク化が困難とされています。
しかしそれ以外の分野では、テレワーク化が進んでいます。それは「テレワーク化しようという意思」が強いからでしょう。
日本では、コロナ禍の中でも印鑑を押すために会社に行かなければならないケースが問題になっています(*5)。電子認証制度などを活用すれば、押印のための出社をなくすことは不可能ではありません(*6)。
業務のテレワーク化を推進するかどうかは、経営者や管理職たちの意思が強く影響していそうです。
*4:https://www.newsweekjapan.jp/kim_m/2020/07/post-19_3.php
*5:https://www.asahi.com/articles/ASN6M75PTN6MULZU009.html
*6:http://houmukyoku.moj.go.jp/toyama/table/QandA/all/qa3.html
まとめ~国民性、企業風土、労働観の差
日本もアメリカも、ウィズコロナ社会では、テレワークが有効な手段の1つであるとの認識は共通しています。ただ両国には温度差があります。
合理性をどの程度重要視するかといった国民性や、上司と部下の関係や、働き方に対する考え方がテレワークの普及率に影響していそうです。
もちろん、テレワーク化すると生産性が落ちる仕事もあります。経営者にも労働者にも、テレワークを賢く利用することが求められます。

「有料求人サイトに登録したものの、思ったように人材が集まらない…」 「せっかく入った人がすぐにやめてしまう…」 そんな悩みが「スカウトマン&サーベイ」ですべて解消されます。 【導入後メリット】 ・通年採用がコスト0円で実現できるようになる ・欲しい人材からの応募が増える ・会社の良いところ良くないところがわかり、強い会社づくりへ一歩踏み出せる ・採用後の労務相談も社労士が無料で対応
おすすめ記事