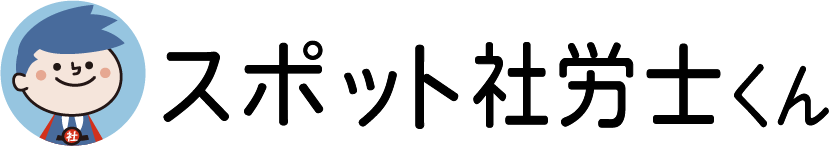手続きの事
2020.12.25
【手続き】従業員のiDeCo加入で会社がやるべきこと
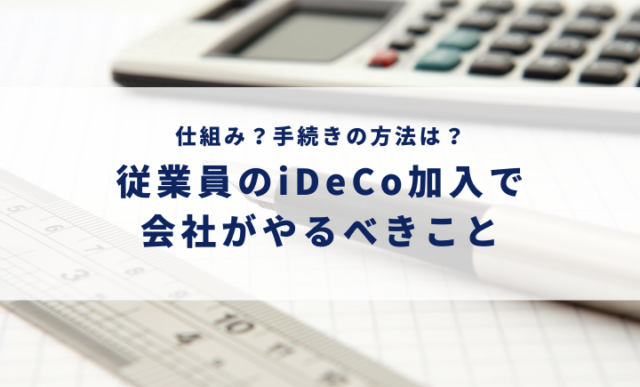
入社予定者からiDeCoを継続したいと言われました。うちでは現状iDeCoの加入者がいないのですが、何か制度を作らなければいけないのでしょうか?
確定拠出年金はポータビリティがあるのが特長です。個人型であるiDeCoは、転職で勤務先が変わっても、新しい会社の企業年金制度の有無によっては継続して掛けることができます。
iDeCoの制度概要と、従業員から加入したいとの申し出を受けたときに会社がすべきことについて、整理しておきましょう。
iDeCoとは
iDeCoとは、2002年からスタートした個人型確定拠出年金のことです。公的年金とは別に、自分で決めた額を毎月積み立てて運用し、60歳以降に受け取ることができる私的年金です。
国民年金基金連合会が実施主体となっており「もうひとつの年金」とも呼ばれています。
iDeCoは、国民年金や厚生年金保険と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。

iDeCoの加入者は年々増えており、2019年3月末時点では1,212,304人となっています。2017年の制度改正により、企業年金に加入している会社員や公務員もiDeCoに加入できるようになったため、近年、加速度的に加入者が拡大している状況です。

2022年10月からは、企業型確定拠出年金に加入している方についてもiDeCoに加入可能となります。老後への不安は若年層にも広がっていますので、今後もさらに加入者は増加すると思われます。
iDeCoの仕組みとは
私的年金であるiDeCoは自分で掛金を決めて拠出し、その掛金を自分で運用し、60歳以降に年金として受け取るという仕組みです。公的年金とは掛金の決め方や運用方法などが異なります。また、直近2020年にも制度が改正されていますので、あわせて確認していきましょう。

○従業員がiDeCoに加入するための社内制度
従業員がiDeCoに加入するにあたって、特に社内規程や労使協定などは不要です。ただし、すでに企業型確定拠出年金を実施している場合は、iDeCoに同時加入できる旨の定めが必要です。既存の規約にこのような定めがない場合は、変更が必要となりますので注意しましょう。
また、この規約は事業所ごとに保管して、加入者が自由に閲覧できる状態にしておく必要があります。
企業型確定拠出年金に従業員が掛金を上乗せする「マッチング拠出」を行っている場合は、iDeCoと同時に利用することはできません。「マッチング拠出」もしくは「iDeCo」のどちらかを選択することになりますので、社内で調整が必要です。
○iDeCoに加入できるのは?
iDeCoに加入できるのは、「65歳未満の国民年金被保険者」です。具体的には(1)~(3)の方が該当します。
(1) 国民年金第1号被保険者である自営業者
※農業者年金の被保険者や国民年金の保険料免除者を除く
(2) 国民年金2号被保険者である厚生年金保険の被保険者
(3) 国民年金第3号被保険者である専業主婦(夫)
会社の発行する保険証を有している方は、(2)に当てはまりますね。
○iDeCoの掛金
iDeCoの掛金は、月額5,000円以上、1,000円単位刻みで、加入者が決定します。加入者自身で負担のない額を定めることができるのはメリットです。ただし、この掛金には、加入している公的年金の種類や企業年金の有無などにより、上限があります。
(1) 自営業者等:月額68,000円まで
・国民年金基金の掛金や国民年金の付加保険料を含んだ限度額
(2) 厚生年金保険の被加入者のうち
・厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施している場合:月額12,000円まで
・企業型年金のみを実施している場合:月額20,000円まで
・企業型年金や厚生年金基金等の年金を実施していない場合:月額23,000円まで
・公務員、私学共済制度の加入者:月額12,000円まで
(3) 専業主婦(夫)等:月額23,000円まで
また、掛金は全額所得控除の対象となりますので、その年の所得税と翌年の住民税が軽減されます。
年末調整時に対応が必要ですね。
○運用方法
iDeCoでは、拠出した掛金を加入者が自分で運用します。運営管理機関が提示している預貯金・投資信託・保険商品等などの運用商品の中から、加入者自身が選びます。複数の商品を組み合わせて選ぶこともできます。
選んだ商品によっては運用で掛金が倍になることもあれば、元本割れをすることもあります。運用は自己責任です。
運用期間中は、税制優遇により運用益が非課税ですので、利益の全額を再投資することができます。
○受取年齢と方法
iDeCoの年金資産は原則として、60歳以降にしか受け取ることができません。受取方法は年金と一時金、あるいはその両方を組み合わせた方法が選択できます。
また、受け取り時の税金にも優遇措置があります。年金で受け取る場合は公的年金等控除が受けられ、一方で、一時金で受け取る場合は退職所得控除が受けられる、という仕組みになっています。

60歳から年金資産を受け取るには、加入期間が10年以上必要です。加入期間が10年未満の場合は加入年数により受給開始可能年齢が繰り下げられます。

事業主の義務とは(会社がすべきこと)
従業員がiDeCoに加入するために、事業主が行わなければならない事務手続きがあります。会社がすべきことを確認しましょう。手続きは、従業員の加入時だけではありません。
【加入時の手続】
(1) 会社として国民年金基金連合会に事業所登録が必須です。
※事業主が給与天引きして掛金を納める場合だけではなく、従業員個人が自分自身で掛金を納める場合にも、事業所登録が必要です。
※事業主が給与天引きして掛金を納付する場合と、従業員自身が個人で掛金を納付する場合では別々の番号登録が必要です。つまり、2パターンの従業員がいる場合、それぞれ登録手続きを行います。(※下記(2)と同時に行います)
(2) 従業員が国民年金基金連合会に提出する「個人型年金加入申出書」の事業者証明に、必要事項を記入して証明します。
※事業所登録がない初回は、「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を提出することで事業所登録できます。(※上記(1))
事業所登録すると書面で番号が通知されますので、次回の証明時からは、登録事業所番号を記入します。

【加入後】
(1) 従業員が事業主払込を希望する場合は、毎月の給与から掛金を天引きし、会社経由で国民年金基金連合会に払込みを行います。
(2) 国民年金基金連合会から、年1回、状況確認の書類が届きます。加入申出時に得た情報をもとに加入者名が記載されていますので在籍の有無を確認。加えて、事業所の資格の確認もあわせて行われます。内容を確認して提出します。
(3) iDeCoの掛金は、年末調整の際に所得控除の対象となります。従業員が個人で掛金を払込している場合、国民年金基金連合会から従業員あてに「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送付されます。この証明書を年末調整の際に提出させ、源泉所得税の計算に反映します。
iDeCoハラスメント
従業員がiDeCoに加入することで、会社の事務手続きは増えます。そのため、会社側がiDeCoに加入を希望する従業員に圧力をかけたり、加入手続きを進めないなどのハラスメントが起きています。「iDeCoハラスメント」、通称「イデハラ」と呼ばれています。残念なことに通称があるほど認知されているハラスメントです。
従業員が自身で掛金を納めている場合でも、事業主には事業所登録や毎年の確認書類の提出手続きが発生し、会社の事務負担は増えます。しかし、軽い気持ちで発した一言が会社の協力義務違反となることもありますので慎重に対応しましょう。
従業員の方がiDeCoに加入している場合、事業主は、「必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない」と法律で定められています(確定拠出年金法第78条)。
こうした事情もあってか、2020年8月の日経新聞記事によると、厚生労働省は2022年秋を目処に、事業主が証明する「事業主証明」の提出を不要とする方針のようです。今後の動きに注目していきましょう。
参考記事:日経新聞|会社員のiDeCo加入、事業主証明を不要に 厚労省
iDeCoプラスについて
「iDeCo+(イデコプラス)」は、中小事業主掛金納付制度のことです。従業員が掛金を拠出している個人型確定拠出年金(個人型DC)に、企業が掛金を上乗せする逆マッチング拠出です。
従業員は、自分が拠出した加入者掛金と、事業主が拠出した事業主掛金をあわせて運用します。
従業員と事業主の掛金の合計は、5,000円から1,000円単位で拠出でき、受取年齢は基本的に60歳です。他の企業年金制度を導入していない会社の従業員は、事業主分と合わせて月額23,000円まで拠出可能です。
従業員が主体の制度であるため、事業主が掛金を全額負担することはできません。あくまでも上乗せの仕組みです。

○事業主のiDeCo+加入条件
(1)企業型確定拠出年金に加入していない
(2)確定給付企業年金・厚生年金基金などの制度を導入していない
(3)従業員300名以下
(4)労使が実施について合意している
iDeCo+では、運営管理手数料などの諸経費は従業員が負担しますので、会社側は費用をかけずに企業年金制度を導入することができるというメリットがあります。
老後の負担を考えて、個人で年金を準備する動きが拡大しています。企業年金制度のない企業に勤めている従業員の中には「iDeCo」や「iDeCo+」の加入を検討する者も増えると思います。
会社として対応を考えておきましょう。
オンラインセミナー(無料)のご案内

ネットで調べてもよくわからない人事労務の情報を手軽にオンラインで学べる! 様々なコンテンツをご用意しております。
スポット社労士くんから加入で
今なら1年間無料‼

毎月の給与計算をもっと楽に簡単にしたい!という皆様朗報です!
今ならクラウド給与ソフトが1年間無料!
関連記事